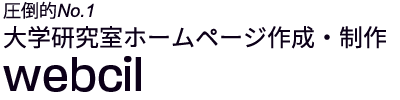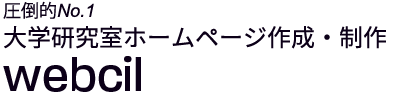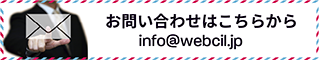ほうじ茶の名前の由来は?
ほうじ茶の由来についてChatGPTに聞いてみました。答えは以下の通り。
ほうじ茶(焙じ茶)の由来について説明しますね 🍵
🌿 基本的な概要
**ほうじ茶(焙じ茶)**は、緑茶を強火で焙煎(ほうじ)して作るお茶です。原料となるのは主に番茶や煎茶、茎茶(くき茶)など。焙煎によってカフェインがやや減り、香ばしい香りとまろやかな味わいが特徴です。
🕰 ほうじ茶の起源
ほうじ茶の起源は 大正時代の京都 にあるといわれています。
- 当時、京都の茶商が売れ残った番茶や古くなった茶葉を焙煎して販売したのが始まりと伝えられています。
- その結果、「香ばしくて飲みやすい」と評判になり、関西を中心に全国へ広まりました。
このように、もともとは茶商の工夫や再利用の知恵から生まれたお茶なんです。
☕ 名前の由来
「ほうじ茶」という名前は、製法そのもの——つまり**「焙じる(炒る)」**という工程に由来します。
「焙じる」→「ほうじる」→「ほうじ茶」という流れですね。
💡豆知識
- 焙煎によって苦味や渋味のもととなるカテキンやカフェインが減少するため、子どもやお年寄りにも人気。
- 茶葉を強く焙じることでできる**香ばしい香り(ピラジン類など)**が、リラックス効果をもたらすとされています。
- 最近では、ほうじ茶ラテやほうじ茶スイーツなどにも応用され、再び人気が高まっています。
なるほど、法事のときにのむお茶ではないのですね。