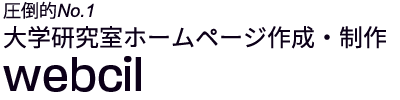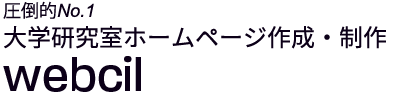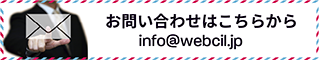日本にはお盆が2種類あるって本当ですか?
少し前に日本は新盆と旧盆の2種類があるという記事をみました。詳しく知りたいので、ChatGPTに「日本にはお盆が2種類あるって本当ですか?」とチャットしてみました。
答えは以下の通り。
はい、本当です!日本のお盆には、大きく分けて「新盆(新のお盆)」と「旧盆(旧のお盆)」という2つの区分があり、加えて地域によって7月・8月・旧暦(7月)の3つの時期に分けて祝われるケースもあります。
1. 「新盆(しんぼん)」と「旧盆(きゅうぼん)」 🕯️
新盆(新のお盆)
- 7月中旬(7月13〜16日頃)に行われるお盆のことです。
- 特に東京をはじめとする首都圏などでこの7月盆が慣習として根付いています。
旧盆(旧のお盆)
- 8月中旬(8月13〜16日頃)に行われるお盆が全国的には主流で、こちらが「旧盆」「月遅れ盆」と呼ばれています。
なぜ違うの?
- 明治維新後の暦の切り替えで、旧暦の7月15日が新暦では8月にずれてしまったため、地域ごとの対応が分かれました。
- 首都圏や農繁期と重なる地域では「新暦=7月15日」に合わせる → 新盆。
- 他地域では、「旧暦の7月15日」に習い → 新暦の8月中旬に祝う → 旧盆。
2. さらに細かい区分:3タイプのお盆
Wikipediaによると、日本のお盆は以下3タイプに分かれます:
- Shichigatsu Bon(7月盆):7月15日前後、都市部や東日本で一般的。
- Hachigatsu Bon(8月盆):8月15日前後、全国的な主流。
- Kyū Bon(旧暦盆):旧暦7月15日、沖縄や奄美などで祝われ、旧暦ゆえ日程が年ごとに変動。
3. 「新盆」の意味(もう一つ)
さらに混乱の原因となるのが、「新盆」という言葉にはもう一つ意味があります:
- 故人が亡くなった後、四十九日を過ぎて迎える最初のお盆(例えば、4月に人が亡くなり7月中旬に初めて迎えるお盆など)。この場合も「新盆」「初盆」と言います。
🧭 まとめ表
| 区分 | 意味・時期の特徴 |
|---|---|
| 新盆(時期) | 新暦7月中旬の一般的なお盆 |
| 旧盆 | 新暦8月中旬の主流お盆(旧暦由来) |
| 旧暦盆 | 旧暦7月15日、地域によって祝う(沖縄など) |
| 新盆/初盆(故人に関する意味) | 故人が亡くなってから最初のお盆 |
✅ 回答まとめ
はい、「日本にはお盆が2種類ある」というのは正しく、
- 一つは 「新盆」(7月盆) と 「旧盆」(8月盆) の時期の違いに基づく区分。
- また「新盆」には、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆という意味もあります。
さらに地域によっては旧暦のお盆を別に祝うケースもあります。
どのタイミング・意味で「お盆」が行われるかは、その地域の歴史的背景(暦のずれや生活スタイル)によって違ってくるのです。
なるほど、お盆って8月中旬だと思っていましたが、東京では7月中旬なのですね。流石、都会は進んでいますね。田舎者にはわかりません。東京の会社は休みになったりするのでしょうか?そこで次に、なぜ東京は新盆なのかを聞いてみました。
答えは以下の通り。
とても良い質問です。「なぜ東京だけが新盆(7月13〜16日頃)なのか?」については、以下のような歴史的・社会的な背景があります。
✅ 東京が「新盆(7月盆)」になった理由
1. 明治の改暦によるズレと都市部の迅速な対応
- 明治5年(1872年)に、日本は旧暦(太陰太陽暦)から新暦(太陽暦)へ移行しました。
- 旧暦7月15日(お盆)は、新暦では8月中旬頃になります。
- 政府は当初、新暦の7月15日をお盆とするよう指導しましたが、農村部では「農繁期と重なる」として反発もあり、旧暦に近い8月15日(旧盆・月遅れ盆)に移した地域が多くなりました。
一方で…
2. 東京は農村ではなく都市であり、農繁期と無関係だった
- 東京では農作業による季節の制約がなかったため、改暦後もそのまま7月15日にお盆を実施しても問題なかったのです。
✅ 他の要因も考えられます
3. 官庁・企業の影響と近代化の象徴
- 東京は政府・官庁の中心地であり、「新暦に準拠する」ことが文明開化・近代化の象徴とされていたため、政府の方針を素直に受け入れた側面もあります。
- また、企業や役所の夏休み(お盆休み)の日程を調整しやすいという実利的な理由もありました。
✅ 結果としての分裂
| 地域 | お盆の時期 | 備考 |
|---|---|---|
| 東京や横浜など首都圏 | 7月13日~16日 | 新暦そのまま=「新盆」 |
| 全国の多くの地域(東北・関西・九州など) | 8月13日~16日 | 旧暦に近い「旧盆・月遅れ盆」 |
| 沖縄など一部地域 | 旧暦7月15日頃 | 「旧暦盆」=毎年変動 |
🧭 まとめ
東京が「新盆(7月盆)」になった理由は:
- 明治の改暦に素直に従った
- 農繁期の影響がない都市だった
- 近代化・中央政府の方針を尊重した
という都市ならではの背景があったからです。
地方では、生活リズムや農業の都合から、あえて「旧暦に近い8月15日」にずらして現在に至っています。
なるほど日本のほとんどは農村部だったので、農繁期と重ならない旧盆のままなのですね。農繁期の影響を受けない都市部だけが新盆に従ったというわけですか。ところで8月の第1週に東北のあちこちで夏祭りが行われますが、お盆と関係あるのでしょうか?ChatGPTに「お盆と東北の夏祭りの関係について教えてください。」とチャットしてみました。
答えは以下の通り。
お盆と東北の夏祭りには、深いつながりがあります。多くの東北の伝統的な夏祭りは、もともとお盆の行事や精霊送り、祖霊信仰と結びついた宗教的意味合いをもって始まったものが多いのです。
✅ お盆と東北の夏祭りの関係
1. お盆=祖先の霊を迎えて送る時期
- お盆(8月13日〜16日頃)は、亡くなった祖先の霊がこの世に帰ってくるとされる行事。
- 人々は精霊棚(しょうりょうだな)を作って迎え火を焚き、墓参りをして霊を迎え、送り火や灯篭流しで霊を見送ります。
- こうした死者の魂を慰める儀式が、やがて「祭り」として地域ごとの形をとって広まりました。
🏮 東北の主な夏祭りとお盆の関係
| 祭り名 | 開催地 | 時期 | お盆との関係 |
|---|---|---|---|
| 青森ねぶた祭 | 青森市 | 8月2~7日 | 七夕行事+お盆の精霊送りが起源。灯籠(ねぶた)を流して邪気や霊を送り出す「流し灯籠」が原型。 |
| 弘前ねぷた祭 | 弘前市 | 8月1~7日 | 眠気を払う「眠り流し」=お盆前の厄祓い儀式が起源。 |
| 秋田竿燈まつり | 秋田市 | 8月3~6日 | お盆の迎え火・送り火を模したとも言われる。提灯は精霊の灯火の象徴。 |
| 山形花笠まつり | 山形市 | 8月5~7日 | 盆踊りの派生。もともと盆踊りの時期に行われていた農民の慰霊と祈願。 |
| 西馬音内盆踊り | 秋田県羽後町 | 8月15~16日 | 完全にお盆のための盆踊り。精霊を慰め、送り出す厳かな雰囲気。 |
| 盛岡さんさ踊り | 岩手県盛岡市 | 8月1~4日 | 鬼退治と豊作祈願が起源だが、お盆前の精霊送りの時期と連動。 |
🔥 キーワード:「精霊送り」や「魂鎮め」
東北の夏祭りには、共通して以下のような意味があります:
- 死者の魂を鎮める(魂鎮め)
- 悪霊や災厄を追い払う(祓い)
- 豊作や無病息災を祈る(神事)
これらは本来、すべてお盆の宗教行事と深く結びついています。つまり、東北の夏祭りの多くは、お盆を彩る「先祖供養の民俗行事」から発展した文化的イベントなのです。
🎆 なぜ今は「観光イベント」に見えるのか?
- 戦後~現代にかけて、これらの祭りは全国的に観光資源として整備され、「踊り」「灯り」「山車(だし)」などの派手な見た目が強調されるようになりました。
- しかし本来は、お盆という静かな宗教行事の一部だったのです。
🧭 まとめ
- 東北地方の夏祭りは、もともとお盆と深く結びついた先祖供養や精霊送りの行事でした。
- 多くは8月上旬~中旬に行われ、お盆の前後に霊を迎え、祀り、送り出すという意味があります。
- 今日では観光イベントとして有名になっていますが、その起源には日本人の死生観や信仰心がしっかりと根付いています。
なるほど、やはりお盆と深い関係があるのですね。でも、なぜ8月中旬に行われずに8月上旬に行われるのでしょうか?ChatGPTに「なぜ東北の夏祭りは8月中旬ではなく8月上旬に行われるのですか?」とチャットしてみました。
とても良い着眼点です。
東北の夏祭りが お盆(8月13〜16日)ではなく、その直前の8月上旬に行われる理由は、主に以下の3つの要因から説明できます:
✅ 1. 「お盆の準備・精霊迎え」としての性格
多くの東北の祭りは、もともと**お盆の準備や精霊を迎えるための行事(迎え火や祓い)**として始まりました。
つまり:
- ねぶた(青森):悪霊や睡魔を「流す(追い払う)」=「眠り流し」や「灯籠流し」が由来。
- 竿燈(秋田):提灯を掲げて祖霊を迎える“擬似的な迎え火”のような行事。
▶️ そのため、「お盆本番の直前」に行うのが自然だったのです。
お盆の“本番”では祖先を静かに迎えて祀るため、賑やかな行事はその前に済ませるのが本来の流れです。
✅ 2. 農作業との両立(お盆本番は家族や農の時間)
東北は農業中心の地域で、お盆の時期は「農繁期の合間の休息」として大切にされてきました。
そのため:
- 祭りはあくまでお盆の“前”に済ませる
- お盆は親戚が集まり、墓参りや祖先供養をする“静かな時間”
- 「祭り→迎え火→お盆→送り火」というリズムが生活に根づいていた
▶️ お盆に派手な祭りをぶつけるのは本来不自然で、心を整える前段階として祭りが位置付けられたのです。
✅ 3. 観光と交通の現代的配慮(昭和後期以降)
戦後~高度経済成長期に入ると、東北の祭りは全国的観光イベントとしての地位を確立します。その際に考慮されたのが:
- お盆(8月13~16日)は帰省ラッシュと重なる → 交通渋滞・宿不足になる
- 観光客に分散して訪れてもらうために、8月上旬に開催を固定した
▶️ たとえば青森ねぶた祭は観光振興と地元行事の両立のために「お盆前に固定」された背景があります。
🧭 まとめ:なぜ8月上旬なのか?
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| ① 精霊迎えの伝統 | お盆前に霊を迎える祓いの行事だった |
| ② 農村の生活習慣 | お盆本番は家族と静かに過ごすため、祭りは前倒し |
| ③ 現代の観光配慮 | 帰省ラッシュを避けて観光時期を分散するため |
なるほど、もともとお盆は静かに休んで、お盆の前の準備としての祭りという位置づけだったのですね。納得です!!!