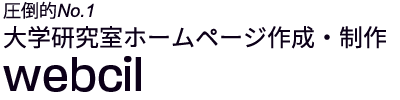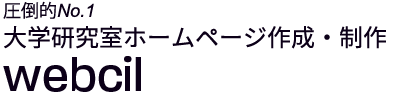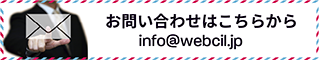猛暑だとセミの数は減りますか?
今年は猛暑ですね。例年よりセミの声が少ない様な気がします。そこで、「猛暑だとセミの数が減りますか?」とChatGPTに聞いてみました。
答えは以下の通り。
はい、猛暑が続くとセミの数が減ることがあります。理由は以下の通りです:
🔥 猛暑によるセミへの影響
1. 地中の幼虫の活動に影響
- セミは多くの時間を地中で幼虫として過ごします(3~7年)。
- 地中の温度が極端に高くなると、乾燥や高温で弱って死んでしまう幼虫も出てきます。
2. 成虫の寿命が縮む
- 成虫になったセミは1~2週間ほどの短い命ですが、猛暑で水分が失われやすく、脱水や熱ストレスで早く死ぬことがあります。
3. 羽化の時期がずれる
- 猛暑や異常気象で、羽化するタイミングがバラバラになることがあります。
- その結果、例年よりセミの鳴き声が少ないと感じることも。
4. 都市部のヒートアイランド現象の影響
- 都市部ではアブラゼミが減り、クマゼミが増える傾向がありますが、猛暑が極端になるとクマゼミすらも減ることがあります。
🐞 実際に起きていること(例)
- 2022年の猛暑では、東京都内の公園でアブラゼミの数が例年の半分以下に減少したとの観測もありました。
- 研究では「猛暑日(35℃以上)が多いと、セミの羽化率が低下する」ことが指摘されています。
📝 まとめ
| 要因 | セミへの影響 |
|---|---|
| 地中の高温・乾燥 | 幼虫が死ぬ、羽化しづらくなる |
| 気温の上昇 | 成虫が早く死ぬ、活動時間が短くなる |
| ヒートアイランド | 種の構成が変わる、全体数が減ることもある |
なるほど、やはり猛暑だとセミの数は減るのですね。それでは、なぜクマゼミの方がアブラゼミよりも猛暑に強いのでしょうか?
答えは以下の通り。
✅ 1. 適応してきた生息地の違い
| セミの種類 | 元々の分布地域 | 気候 |
|---|---|---|
| アブラゼミ | 関東〜中部、内陸向き | 比較的温帯(中緯度) |
| クマゼミ | 九州・西日本(沿岸地域) | 暑く湿度の高い亜熱帯に近い気候 |
- クマゼミはもともと暑い地域に多く生息していたため、高温多湿に強い遺伝的適応を持っています。
- 一方、アブラゼミはやや涼しい地域の森を好むため、猛暑によるストレス耐性が低いのです。
✅ 2. 羽の構造による放熱効果の違い
- 近年の研究で、クマゼミの翅(はね)には特殊な構造があり、
- 赤外線を効率よく放射して体温を下げる効果(放熱効果)があることが判明。
- いわば「天然の放熱フィン」のような働きです。
- アブラゼミの羽にはそのような構造がなく、体温調整が苦手。
✅ 3. 都市環境への適応力
- クマゼミは
- 街路樹やコンクリートの熱環境にも強い。
- 人家の近くや都市公園でも繁殖できる。
- アブラゼミは
- 森林性で、特に幼虫期は湿った落ち葉や柔らかい土壌が必要。
- 都市の硬い土や乾燥した地中では生き残りにくい。
🔍 事例:東京での勢力交代
- 1990年代以降、東京都心でクマゼミが急増し、アブラゼミが減少。
- ヒートアイランド現象により、
- 地表温度が40℃を超える場所も多く、
- アブラゼミが生き残れず、クマゼミが北上・定着したと考えられています。
📝 まとめ
| 比較項目 | クマゼミ | アブラゼミ |
|---|---|---|
| 暑さへの耐性 | 高い(赤外線放射+高温順応) | 低い |
| 生息環境 | 都市・沿岸・温暖地域 | 森林・やや涼しい場所 |
| 羽の特徴 | 放熱構造あり(体温を下げやすい) | 特に放熱構造なし |
| 都市での適応力 | 高い | 低い |
| 近年の分布傾向 | 北上中(関東にも定着) | 減少傾向 |
なるほど、クマゼミはもともと南の暑いところが生息地でだんだん北上してきているのですね。ところで北海道にもセミはいるのでしょうか?
答えは以下の通り。
🪲 北海道にいる主なセミの種類(代表例)
| 種類 | 特徴・分布 |
|---|---|
| エゾゼミ | 北海道を代表するセミ。7月中旬〜8月に鳴く。 「ジーーージジジ…」と鳴く。 |
| コエゾゼミ | エゾゼミよりもやや小さく、鳴き声も高く軽い。 針葉樹林を好む。 |
| アカエゾゼミ | 高地や涼しい地域に生息。寒冷地向きのセミ。 |
| ヒグラシ | 北海道南部(道南)に分布。 「カナカナ…」という鳴き声。 |
| ミンミンゼミ | 最近は札幌など都市部に少数定着の傾向(本州からの北上)。 |
🌡 北海道の気候とセミ
- セミは地中で数年を過ごし、夏に羽化します。
- 北海道の冷涼な気候では、セミにとって地中の温度が低いため、
- 羽化までの年数が長くなる傾向(7年以上の例も)。
- 種類によっては、冷害や凍結に耐える特殊な適応が見られます。
🗺 分布の地域差
| 地域 | セミの種類と特徴 |
|---|---|
| 道東・道北 | エゾゼミ・コエゾゼミなど寒冷地型が中心 |
| 道央(札幌) | 都市部にエゾゼミや、近年はミンミンゼミも出現 |
| 道南 | 本州に近く比較的温暖なため、 ヒグラシやニイニイゼミもまれに確認されることあり |
🐣 なぜセミは北海道に少ないのか?
- 冬の地中温度が低すぎると、幼虫が凍死するリスクがある。
- また、セミは年平均気温10〜11℃以上でないと繁殖しにくいと言われています。
- そのため、セミの分布は日本列島の気温帯と一致しており、北海道では限られた種類しか生き残れないのです。
✅ まとめ
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| セミの有無 | 北海道にも生息している(主にエゾゼミ類) |
| 種類の多さ | 本州より少ない(5〜6種類程度) |
| 気候との関係 | 冷涼で湿った地中に適応した種類が多い |
| 最近の変化 | 都市の温暖化で、本州型のセミ(ミンミンゼミなど)が進出中 |
なるほど、寒すぎてもセミは生き残れないのですね。興味のある方は、エゾゼミを画像検索してみてください。暑さのせいで本州のミンミンゼミが北上しているのですね。いつか北海道でアブラゼミやクマゼミが観測されるかもしれません。