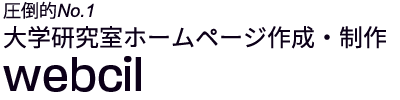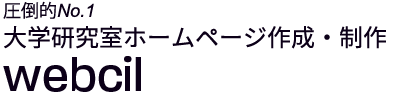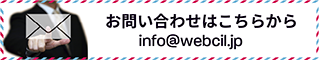日本ではサンマが獲れなくなっている?
日本ではサンマが獲れなくなっているかChatGPTに聞いてみました。答えは以下の通り。
はい、日本ではサンマ(秋刀魚)の漁獲量が著しく減少しています。以下にその背景と現状を整理します。
🎣 漁獲量の減少状況
- 戦後から1990年代までは、年間20万〜30万トン台の漁獲がありましたが、2008年には約35万トンを記録。その後減少が続き、2022年には約1 万8,000トンと過去最低を更新しました(2008年と比較するとわずか5%程度)Nippon+15Nippon+15農林水産省+15ウェザーニュース+2fra.affrc.go.jp+2。
- 2023年時点では、サンマを含むサケ・スルメイカとの主要魚種合計が2014年から約80%減少しており、サンマも例外ではありません環境省デコ活。
📉 減少の原因
1. 漁場の沖合化(分布の遠洋化)
- 2010年以降、サンマの個体群は日本近海から遠く離れた沖合へと移動するようになりました。これにより漁場が遠くなり、漁船の往復時間や燃料コストが増加していますfra.affrc.go.jp+5農林水産省+5lib.suisan-shinkou.or.jp+5。
- 2024年時点でも港から1〜2日かかる漁場で操業するのが主流となっており、漁効率が非常に低下していますlib.suisan-shinkou.or.jp。
2. 海洋環境・食物環境の変化
- 親潮(千島海流)の南下が弱まっており、サンマが近海に戻ってこない傾向が続いています。これは海水温の上昇や潮流の変化が影響していると考えられますウェザーニュース+2環境省デコ活+2。
- プランクトンなど餌資源の減少により、個体の成長も妨げられ、近年ではサンマの平均体重がさらに小型化していますウェザーニュース。
3. 海外漁船の参入と国際競争
- 中国や台湾を含む外国船による公海での操業が増え、漁場での競争が激化しています。これにより、日本漁船による漁獲量が相対的に減少しました魚が消えていく本当の理由 – サステナビリティ 水産資源管理 ノルウェー 漁業。
- 北太平洋漁業委員会(NPFC)による漁獲枠設定は行われていますが、枠が実際の漁獲を上回る設定となっており、資源保護に十分な効果を発揮していません魚が消えていく本当の理由 – サステナビリティ 水産資源管理 ノルウェー 漁業。
🍣 価格や消費への影響
- 漁獲量が激減したことで価格は高騰。2022年には1kgあたりの市場価格が2010年比で3倍以上に上昇し、かつての秋の庶民的な味覚から高級魚に様変わりしています環境省デコ活。
✅ 結論:日本ではサンマは「獲れなくなっている」
- 漁獲量は過去最低水準が続いており、漁場が遠洋化・魚が小型化・取れる場所に来ないといった状況が続いています。
- この傾向は海洋環境・気候変動・国際的漁業圧力という複合要因によるもので、簡単に改善できるものではありません。
📌 今後の見通しと対応
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資源管理 | 科学的根拠に基づく漁獲枠の設定と、国別配分の再検討が必要です魚が消えていく本当の理由 – サステナビリティ 水産資源管理 ノルウェー 漁業Nippon。 |
| 環境変化の調査 | 海水温・潮流・餌環境の継続的なモニタリングが不可欠です。 |
| 外国船との協調 | 国際協定の運用強化や違法操業監視の強化によって漁圧を管理する必要があります。 |
なるほど、地球温暖化以外にも中国船などが先に獲ってしまうのが原因なのですね。サンマの値段も3倍になっています。政府がしっかりしてもらわなければ困ります。20年近く前のことですが、以前東北に住んでいたときに行った女川サンマ祭りのサンマが脂がのっていてとってもおいしかったです。