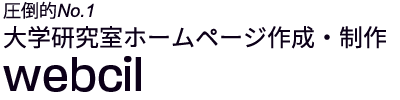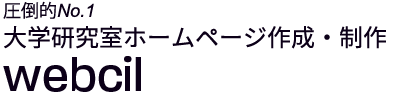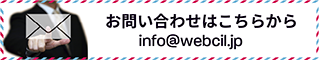襖のサイズは何尺ですか?
尺という日本の伝統的な長さの単位。1尺は30.3cmです。どのようにして尺という長さが決まったのか?また襖のサイズは何尺なのかChatGPTに聞いてみました。
答えは以下の通り。
いいご質問です。襖(ふすま)は障子と同じく建具の一種で、日本建築では「畳の寸法」に合わせて作られてきました。そのため、地方や時代によって多少差はあるのですが、基本は次の通りです。
標準的な襖の寸法(尺貫法)
- 高さ:6尺(約182cm)前後
- 幅:3尺(約91cm)前後
つまり「6尺 × 3尺」がもっとも一般的な襖サイズです。
これを現代のメートル法で換算すると、だいたい 180cm × 90cm 程度になります。
バリエーション
- 京間(本間)サイズ
- 高さ:約6尺3寸(191cm)
- 幅:約3尺1寸5分(95.5cm)
→ 畳が大きい関西地方に多い。
- 中京間サイズ
- 高さ:約6尺(182cm)
- 幅:約3尺(91cm)
→ 東海・北陸に多い。
- 江戸間(関東間)サイズ
- 高さ:約5尺8寸(176cm)
- 幅:約2尺9寸(88cm)
→ 畳が小さい関東地方に多い。
まとめ
襖の大きさは地域差がありますが、基準は 高さ6尺 × 幅3尺。
つまり「182cm × 91cm」程度が標準です。
なるほど、襖は6尺×3尺なのですね。それでは1尺はどのようにして決まったのでしょうか?
答えは以下の通り。
良いところに目をつけられましたね!
1尺が決まった背景
「尺(しゃく)」は、日本の長さの基本単位ですが、その起源は古代中国にさかのぼります。
1. 人の体の寸法が基準
- もともと「尺」とは 人の腕の長さ(肘から指先まで) を意味していました。
- つまり、自然に誰でも使える「体のスケール」を基準にしたのです。
- これは世界中でよくあることで、ヨーロッパの「フィート(足の長さ)」や「インチ(親指の幅)」と同じ発想です。
2. 中国からの伝来
- 古代中国では「周」や「秦」の時代にすでに「尺」が統一単位として整えられていました。
- 日本も律令制の中で唐から度量衡(長さ・重さ・体積の基準)を取り入れ、そこから「1尺 ≒ 30.3cm」が定着していきました。
3. なぜ30.3cmになったか
- 中国でも時代によって「1尺」の実寸は違いました(23cmくらい~33cmくらい)。
- 日本は平安時代~江戸時代にかけて、建築や織物などで広く使われ、最終的に「曲尺(かねじゃく)」=約30.3cm が標準となりました。
- これは大工道具や畳の寸法に深く結びつき、現在も建築分野で「尺モジュール」として残っています。
まとめ
- 由来: 人の腕の長さ(肘から指先)。
- 伝来: 中国から律令制とともに輸入。
- 統一: 江戸時代に「曲尺 1尺=約30.3cm」が基準に。
なるほど、尺は肘から指先までの長さだったのですね。インチが親指の幅ということも初めて知りました。