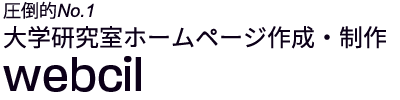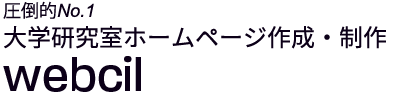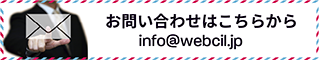リンクページの英訳はLinkとLinksのどちらが適切ですか?
研究室ホームページにおいて、研究業績のページはPublicationsとsをつけるのが通常です。リンクのページはこれまでLinkとしていましたが、Linksの方が正しいと思いChatGPTに確認してみました。
答えは以下の通り。
あなた:
リンクページの英訳はLinkとLinksのどちらが適切ですか?
ChatGPT:
良い質問です。「Link」と「Links」のどちらが適切かは、そのページの内容によって決まります。
- Link(単数形)
そのページに掲載されているリンクが 1つだけ の場合や、1つのリンク先を強調する場合に使われます。 - Links(複数形)
通常、研究室ホームページや個人サイトの「リンク集」のように、複数の関連サイトや外部ページをまとめて紹介する場合はこちらが自然です。
👉 一般的な研究グループや研究者のホームページでは、複数の関連機関・研究者・学会サイトなどを掲載することが多いため、「Links」 がよく使われます。
もし「リンクが1つしかないが、将来的に増える予定がある」場合でも、最初から Links にしておくと自然です。
ご希望なら、実際の海外研究室サイトでの使われ方(「Link」か「Links」か)の事例を調べて比較してみましょうか?
あなた:
Linkの例を教えてください。
ChatGPT:
はい、「Link(単数形)」を実際に使っている例は少数ですがあります。特徴としては 「特定の1つの重要なリンク先だけを示す」 場合に用いられています。
「Link」の具体例
- 企業や研究機関の公式サイトで、関連母体サイトへの導線
例:- ページ下部に “Link: University of Tokyo” として、所属大学への単一リンクを置く。
- 個人研究者のサイトで、自分の所属研究室や大学サイトだけを紹介
例:- 「Link」ページに自分の ORCID プロフィールへのリンクだけを掲載。
- 「Link」ページに所属機関(学部トップページ)のリンクだけを掲載。
- 小規模プロジェクトやイベントページ
例:- 国際会議のWebサイトで「Link」と題し、主催学会の公式ホームページだけを紹介。
海外サイトでの実例(英語圏の慣習)
- ドイツやフランスの研究者個人ページなどで「Link」というページ名があり、その中に 所属大学の公式サイトだけ が置かれているケースが見られます。
- 一方で、アメリカやイギリスの大学研究室では、ほとんどが「Links(複数形)」を使っています。
🔎 まとめると:
- Link = 特定の1つを強調する場合(例:所属先サイト、ORCID、学会公式ページ)
- Links = リンク集・複数掲載する場合(例:学会、共同研究者、関連機関など)
なるほど、リンクが複数あるときは複数形が正しいのですね。今後改めるようにさせていただきます。既にLinkで納品させていただいたかがたくさんおられますが大変失礼いたしました。ご希望がございましたら訂正させていただきます。