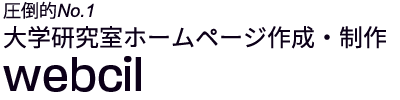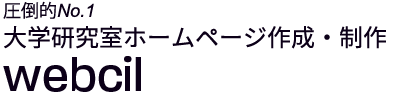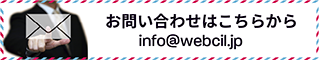「星はすばる」は誰の言葉?
「星はすばる」は星の中ではすばるが一番綺麗という意味です。いったい誰のことばでしょうか?ChatGPTに聞いてみました。
答えは以下の通り。
「星はすばる」という言葉は、清少納言の随筆『枕草子』の一節です。
冒頭近くの「春はあけぼの」で有名な『枕草子』の中に、自然やものごとの美しさを列挙していく章段があり、その中で
星はすばる。彦星。夕づつ。よばひ星。よく見れば、ひとつふたつ、ほどなく消えぬるも、をかし。
と書かれています。
ここで「すばる(昴)」はプレアデス星団のことを指し、日本でも古くから親しまれてきた星の名前です。
つまり、「星はすばる」という表現は、平安時代の女流文学者・清少納言の言葉になります。
なるほど、清少納言の言葉だったのですね。枕草子の一説です。
星はすばる。彦星。夕づつ。よばひ星。よく見れば、ひとつふたつ、ほどなく消えぬるも、をかし。の意味についてChatGPTに聞いてみました。
いい質問ですね😊
いただいた文は『枕草子』の「星はすばる…」の一節を少し意訳・改作した形になっています。
原文
星はすばる。ひこぼし。ゆふづつ。よばひ星、すこしをかし。尾だになからましかば、まいて。
あなたの提示した形
星はすばる。彦星。夕づつ。よばひ星。よく見れば、ひとつふたつ、ほどなく消えぬるも、をかし。
これは後世の注釈や子ども向けの現代語訳で付け加えられた説明に近い言い回しです。
意味をまとめると――
現代語訳
「星といえば昴(すばる)が美しい。彦星(夏の大三角のひとつ、わし座のアルタイル)も、宵の明星(金星)もよい。流れ星(よばひ星)も、しみじみと趣がある。よく見ていると、ひとつふたつとすぐに消えてしまうのも、なんとも風情がある。」
解説
- すばる:プレアデス星団。小さな星が集まって輝く様子が美しい。
- 彦星:わし座のアルタイル。七夕の伝説で織姫と対になる星。
- 夕づつ:夕方にひときわ明るく輝く金星。
- よばひ星:流れ星のこと。「呼ばふ」=求婚の意から、夜に一瞬光って消える様子を重ねたとも。
- よく見れば…:これは清少納言自身の文ではなく、後代の注解。「流れ星はすぐに消えてしまう、そのはかなさもおもしろい」という意味を補足している。
👉 まとめると、この文は 「星々の中で、昴・彦星・宵の明星・流れ星がとくに美しい。流れ星がすぐに消える儚ささえも、趣深く感じられる」 という意味です。
なるほど、アルタイルも金星も流れ星も綺麗です。昨日は、私は天体観測に行きましたが、特に金色の大きな流れ星を見ることができました。清少納言の時代の空はどれくらい綺麗だったのでしょうか?